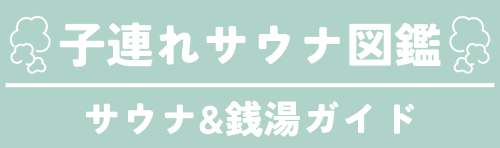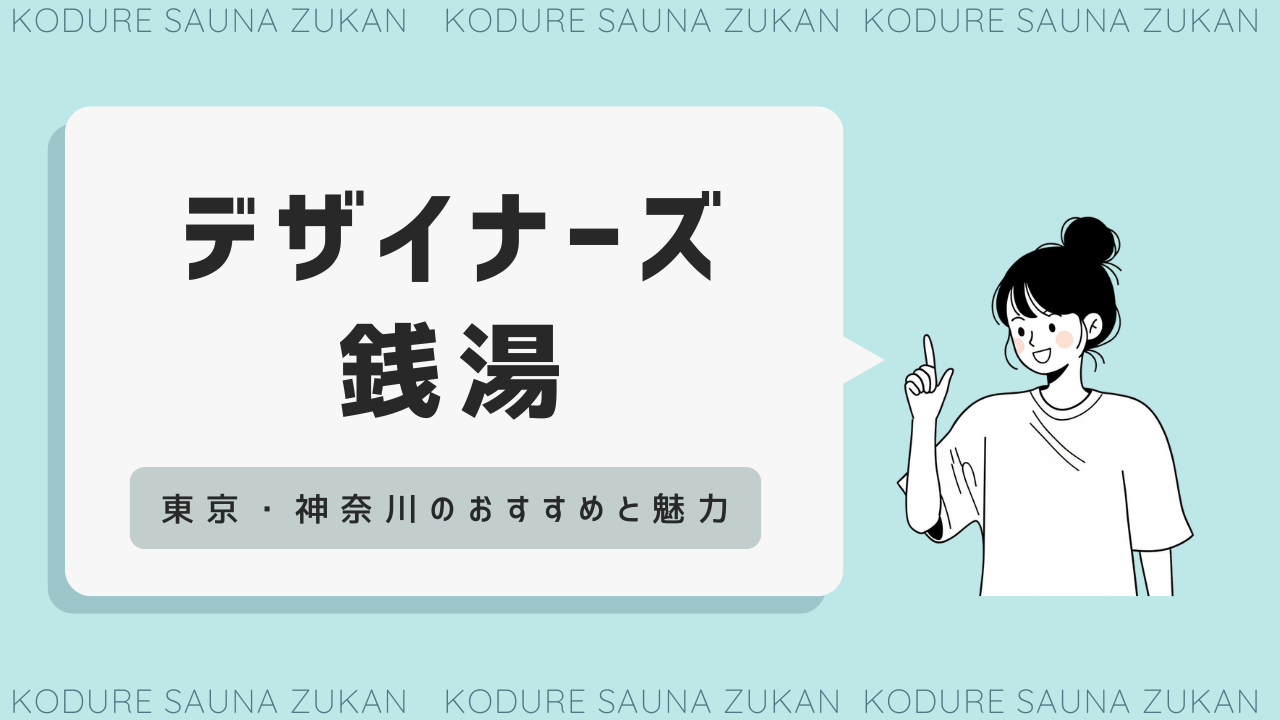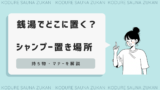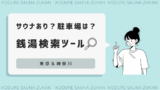「デザイナーズ銭湯」という言葉を耳にする機会が増えていませんか。昔ながらの銭湯とは少し違う、おしゃれな空間が話題です。そもそもデザイナーズ銭湯とは何なのか、なぜ今注目されているのか気になる方も多いでしょう。この記事では、東京や神奈川エリアを中心とした注目のデザイナーズ銭湯の魅力に迫ります。単に清潔でおしゃれなだけでなく、こだわりのサウナや、銭湯文化の象徴とも言える美しい壁絵が現代的にアレンジされている点も見逃せません。日頃の疲れを癒す、新しいリフレッシュスポットをご紹介します。
- デザイナーズ銭湯が注目される背景や理由
- 従来とは異なるデザイナーズ銭湯の空間的な特徴
- 東京や神奈川エリアで訪れることができる銭湯の具体例
- サウナや壁絵など注目すべき設備やこだわり
デザイナーズ銭湯が急増する理由
- デザイナーズ銭湯とは?
- 銭湯業界が直面する経営課題
- 代替わりが促すリノベーション
- 「古い」イメージを払拭する空間
- 清潔感とおしゃれさで集客
デザイナーズ銭湯とは?

デザイナーズ銭湯とは、一般的に、昔ながらの銭湯を大規模にリノベーションし、現代的でおしゃれな施設として蘇らせた銭湯を指します。
単なる設備の入れ替えといった「リフォーム」とは異なり、建築家や専門の設計事務所が空間全体のコンセプト設計から関わる「リノベーション」である点が最大の特徴です。例えば、データベース内の多くの銭湯設計に関わっている「今井健太郎建築設計事務所」のように、その土地の歴史や銭湯の個性を汲み取りつつ、斬新なアイデアで空間を再構築しています。
多くの場合、設備の老朽化に伴うリニューアルを機に、単なる設備の刷新に留まらず、プロデュースを手掛けるケースが目立ちます。これにより、従来の銭湯が持つ「地域のコミュニティハブ」としての温かみを継承しながらも、デザイン性や快適性という新しい価値が付加されています。
結果として、古くからの常連客である高齢層だけでなく、これまで銭湯に馴染みの薄かった若者層や、デザイン・清潔感を重視する女性客からも注目を集めるようになり、新たな客層の開拓に成功しています。
銭湯業界が直面する経営課題

デザイナーズ銭湯が増加している背景には、銭湯業界全体が直面している非常に厳しい経営環境があります。
最大の要因は、言うまでもなく家庭への内風呂の普及です。これにより、公衆浴場としての銭湯の需要は長期的に減少し続けてきました。厚生労働省の「衛生行政報告例」によれば、公衆浴場(一般公衆浴場)の施設数はピーク時の1968年度には全国で18,325軒ありましたが、2022年度には3,123軒と、大幅に減少しています。(出典:厚生労働省「衛生行政報告例」)
さらに、施設の老朽化が進んでも、配管の引き直しやボイラーの交換など、大規模改修には多額の投資が必要となるため、資金調達が難しいという現実的な問題もあります。
加えて、経営者の高齢化に伴う後継者不足も深刻な課題です。事業を継続できずに廃業を選ぶケースも少なくありません。近年では、追い打ちをかけるように原油価格の高騰に伴う燃料費や光熱費が急騰しており、銭湯の経営をさらに圧迫する大きな要因となっています。
代替わりが促すリノベーション

前述の通り、多くの銭湯が廃業の危機に直面する一方で、廃業ではなくリノベーションという積極的な道を選ぶ施設も増えています。その多くは、創業者の祖父母や親から事業を引き継いだ、2代目や3代目といった若い世代の経営者への代替わりがタイミングとなっています。
若い世代の経営者は、従来のままの経営スタイルでは立ち行かなくなるとの強い危機感を持ち、新しい時代に合った銭湯のあり方を模索します。そこで、ただ設備を新しくするだけでなく、デザイン性や快適性を劇的に高める「デザイナーズ銭湯」として再生させ、新たな客層を呼び込もうと考えるのです。
リノベーションの資金調達においても、金融機関からの融資に加え、クラウドファンディングで支援を募ったり、国の事業再構築補助金などを活用したりと、現代的な手法を取り入れるケースも見られます。
リノベーション後は、InstagramやX(旧Twitter)などのSNSを駆使した情報発信や、オンラインでのオリジナルグッズ販売など、運営スタイルそのものもアップデートされます。これは、銭湯という文化を守りつつ、現代のニーズに合わせて経営自体を進化させようとする、力強い取り組みと言えるでしょう。
「古い」イメージを払拭する空間

従来の銭湯に対して、一部の人々は「ボロい」「暗い」「衛生面が心配」といったネガティブなイメージを持っているかもしれません。デザイナーズ銭湯は、こうしたマイナスイメージを根本から覆す、徹底した空間づくりを特徴としています。
例えば、かつて番台があった場所は、高級ホテルのラウンジやおしゃれなカフェのように洗練されたフロント・ロビースペースへと変わります。浴室は、コンクリート打ちっぱなしの壁に間接照明を効果的に配置したり、モダンなタイルワークを施したりするなど、従来の銭湯のイメージとは一線を画すデザインが採用されます。
脱衣所も、単に服を脱ぎ着する場所ではなく、清潔感と機能性を重視したモダンな空間へと生まれ変わります。BGMにジャズやアンビエント音楽を流し、リラックスできる雰囲気づくりにこだわる施設も増えました。
特に渋谷の「改良湯」や新宿の「万年湯」などは、照明の明るさを抑え、光と影のコントラストを巧みに利用することで、まさに「都会の隠れ家」といった特別な雰囲気を演出しています。
アメニティにもこだわりが見られます。備え付けのシャンプーやコンディショナーが用意されているのはもちろん、女性用のパウダールームには高性能なドライヤーが設置されるなど、ソフト面での充実も図られています。このように空間全体をデザインし直すことで、銭湯に馴染みがなかった若者や、清潔感を特に重視する女性客でも、安心して快適に過ごせる場所へと変化させています。
清潔感とおしゃれさで集客

デザイナーズ銭湯の最大の武器は、その「清潔感」と「おしゃれさ」という明確な付加価値です。
前述の通り経営が厳しい銭湯業界において、ただお湯を提供するだけでは、家庭風呂や他の温浴施設との競争に勝つことが難しくなっています。そこで、デザインの力で空間の魅力を最大限に高め、日常とは少し違う特別なリラックス体験を提供することで、他の施設との決定的な差別化を図っています。
この戦略には二つの方向性が見られます。一つは、新宿区の「松の湯」のように、旧店舗で使われていたペンキ絵やエントランスの壁画を再生利用し、昔ながらの銭湯の趣や歴史を大切に残しながら、現代的な快適さとスタイリッシュに融合させるアプローチです。
もう一つは、練馬区の「久松湯」のように、美術館と見紛うような斬新な建築デザインを採用し、プロジェクションマッピングを導入するなど、これまでの銭湯の常識を覆すエンターテインメント性で注目を集めるアプローチです。
どちらのアプローチも、東京都内であれば、多くの場合、一律の公衆浴場入浴料金で利用できます。東京都の入浴料金は、物価高騰の影響を受けつつも、大人550円(2025年10月現在)と定められています。(出典:東京都福祉局「公衆浴場入浴料金」)
この圧倒的なコストパフォーマンスの高さ、つまりワンコイン程度で洗練された非日常空間を体験できることが、多くの人々を惹きつける大きな理由となっています。
デザイナーズ銭湯の魅力と特徴
- 東京で訪れたい注目スポット
- 神奈川にも広がる新たな銭湯
- こだわりが光るサウナ設備
- 空間を彩るアートな壁絵
- デザイナーズ銭湯で心身リフレッシュ
東京で訪れたい注目スポット

東京は、まさにデザイナーズ銭湯の激戦区であり、最先端のトレンド発信地と言えます。渋谷や中目黒といったファッション感度の高いエリアから、練馬や中野などの住宅街、さらには下町の風情が残る墨田や文京に至るまで、都内全域で個性豊かで革新的な施設が次々と誕生しています。
特に近年はサウナブームとも強力に連動し、SNSを通じて魅力的な空間やサウナ体験、こだわりの水風呂などがリアルタイムで共有されています。これにより、デザイナーズ銭湯は単なる近所の入浴施設としてではなく、わざわざ足を運ぶ「目的地」として確立され、「銭湯巡り(湯巡り)」を楽しむカルチャーが若者を中心に根付きつつあります。
ここでは、特に注目したい東京の代表的なデザイナーズ銭湯を、その特徴とともにご紹介します。コンセプトやデザインの違い、お湯やサウナのこだわりなど、各施設の個性を比較するのも「湯巡り」の醍醐味です。
東京の注目デザイナーズ銭湯リスト
| 銭湯名 | エリア | 特徴 |
| 改良湯 | 渋谷区 | 「渋谷 CULTURAL CROSSING」がコンセプト。Gravityfreeによるクジラの壁画が象徴的。シックな内装と肌に優しい軟水が特徴。アウフグースも行われるロウリュサウナと外気浴スペースも完備。 |
| 光明泉 | 目黒区 | 中目黒駅近。白を基調としたシンプルモダンな空間。若手作家によるポップな富士山の壁画や、3階の開放的な露天風呂が人気。高濃度炭酸泉も楽しめます。 |
| 久松湯 | 練馬区 | 2015年度グッドデザイン賞受賞。美術館と見紛うモダン建築が特徴。浴室でのプロジェクションマッピングによる光の演出や、ナトリウム塩化物強塩の天然温泉(露天風呂)が楽しめます。 |
| 黄金湯 | 墨田区 | スキーマ建築計画が設計。番台がビアバー兼DJブースになっており、湯上がりも楽しめるのが革新的。ほしよりこ氏の壁画もユニーク。2階に宿泊施設も併設し、水曜は男女入れ替え日です。 |
| 万年湯 | 新宿区 | 新大久保にある都会の隠れ家。明るい鶴のモザイクタイル絵が美しく、光の演出が神秘的な水風呂や、高温のあつ湯(46度前後)が特徴。シックな大人の雰囲気が漂います。 |
| 南青山 清水湯 | 港区 | 表参道駅徒歩2分。創業100年超の老舗がリニューアル。清潔感あふれる空間と高濃度炭酸泉、シルク風呂など多彩な浴槽が揃い、特に女性からの人気が高い施設です。 |
| 松本湯 | 中野区 | 高級旅館のような和モダンなデザイン。「サウナーの聖地」とも称される。多彩なジェットバス、ReFaシャワーヘッド、オートロウリュサウナと深い水風呂(男湯150cm)が絶大な支持を集めます。 |
| ふくの湯 | 文京区 | 高級旅館のような落ち着いた佇まい。「大黒天の湯(黄金富士)」と「弁財天の湯(赤富士)」が週替わり。人工ラドン温泉や天然生薬100%の薬湯も楽しめます。 |
| COCOFURO たかの湯 | 大田区 | カジュアル&スタイリッシュな空間が特徴。名物の「ミュージックロウリュ」と「爆風オートロウリュ」、そして水温8度(変動あり)の強冷水風呂がサウナーに人気。炭酸泉やあつ湯も完備。 |
ご紹介する情報は記事執筆時点のものです。
特にデザイナーズ銭湯は人気が高く、サウナの待ち時間が発生したり、土日祝は混雑したりすることが予想されます。
また、定期的なメンテナンス休業や、「黄金湯」のように男女入れ替え日が設定されている施設もあります。
訪問前には必ず各銭湯の公式サイトや公式X(旧Twitter)などで、最新の営業時間や混雑状況、サウナの利用ルールなどを確認することをおすすめします。
上記で紹介した施設は、東京のデザイナーズ銭湯のほんの一例です。
この他にも、スカイツリーを望む半露天風呂が名物のビル型銭湯「御谷湯」(墨田区)、黒湯の天然温泉と2種の浴室が日替わりで楽しめる「戸越銀座温泉」(品川区)、「無」をコンセプトにした日常を忘れるシックな空間の「松の湯」(新宿区)、レトロなタイル絵と五色のステンドグラスが美しい「五色湯」(豊島区)、円形のペンキ絵が珍しい「文化浴泉」(目黒区)、緑豊かな狛江の天然水を使った「狛江湯」(狛江市)など、魅力的なデザイナーズ銭湯が都内各所に点在しています。
立地やデザイン、サウナの有無、お湯の種類(天然温泉、軟水、炭酸泉など)も様々です。ぜひご自身の好みやその日の気分に合わせて、お気に入りの一軒を見つけてみてください。
神奈川にも広がる新たな銭湯
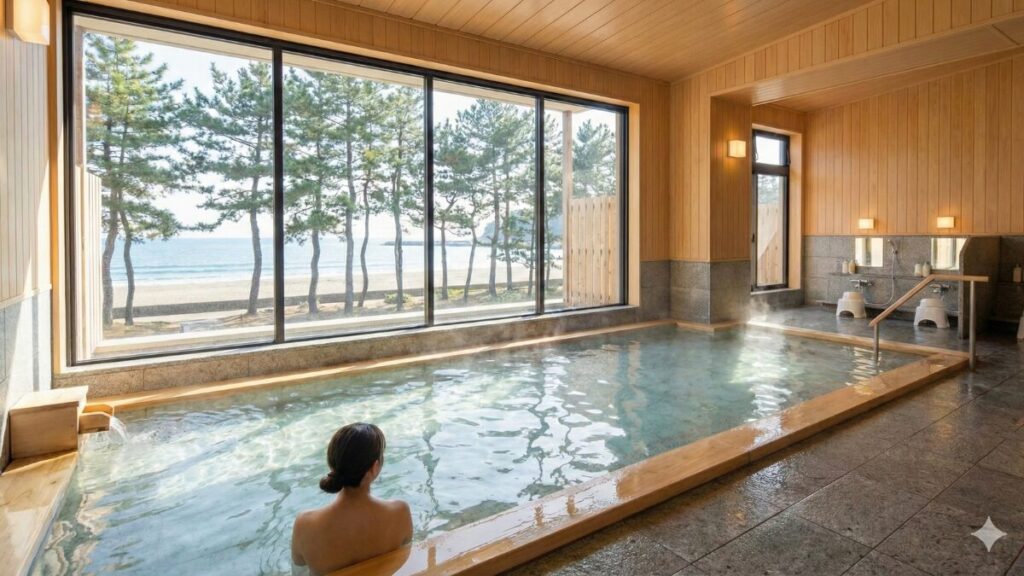
デザイナーズ銭湯へのリノベーションの流れは、東京だけでなく、ベッドタウンである神奈川県にも確実に広がっています。東京と同様に、神奈川県内にも古くから地元住民に愛されてきた銭湯が数多く存在しますが、やはり施設の老朽化や管理負担の増大といった課題に直面しています。
このため、廃業という選択ではなく、現代的な感性を取り入れてスタイリッシュに生まれ変わらせることで、事業を承継し、新たな客層を呼び込もうとする動きが活発化しているのです。
東京からのアクセスも良いため、週末の小旅行気分で神奈川のデザイナーズ銭湯を巡る「湯巡り」も人気を集めています。
千年温泉(川崎市高津区)
神奈川県内におけるデザイナーズ銭湯の代表格の一つが、JR南武線「武蔵新城駅」から徒歩圏内の住宅街に佇む「千年温泉(ちとせおんせん)」です。1964年(昭和39年)創業の歴史ある老舗銭湯が、2018年に全面リニューアルを果たし、地域住民だけでなく遠方からもファンが訪れる人気の施設となっています。
この銭湯の最大の特徴は、館内全体を貫く「大正ロマン」という明確なコンセプトです。リノベーションにあたり、ただ新しく綺麗にするだけでなく、古き良き時代のノスタルジーと現代的な快適性を高いレベルで融合させることに成功しています。
エントランスを抜けると、まず目を引くのが印象的なステンドグラスです。浴室の壁面にも、こだわりのレトロモダンなデザインタイルがふんだんに使われており、まるで大正時代にタイムスリップしたかのような、どこか懐かしくも新しい、ノスタルジックな雰囲気を醸し出しています。
もちろん、デザイン性だけでなく、お湯の質にも強いこだわりが感じられます。千年温泉の最大の魅力は、東京や神奈川の銭湯ではお馴染みの「黒湯」の天然温泉を楽しめる点にあります。露天の岩風呂に注がれる黒湯は、植物由来の有機物(フミン酸など)を豊富に含んだアルカリ性の温泉で、肌がすべすべになる感覚が期待できると言われています。都心部に近い住宅街で、本格的な天然温泉に浸かれるのは大きなメリットでしょう。
内湯の設備も充実しています。近年、多くのデザイナーズ銭湯で導入されている高濃度炭酸泉も完備しており、ぬるめの湯温(約38度設定)でゆっくりと時間をかけて体を温めることができます。さらに、ミクロの泡が肌を優しく包み込むシルキーバスや、日替わりの薬湯、各種ジェットバスなども揃っており、様々なお風呂を巡る楽しさがあります。
一方で、訪問の際にはいくつか注意点もあります。一般的なスーパー銭湯とは異なり、洗い場にシャンプーやボディソープの備え付けはありません。そのため、持参するか、フロントで販売されているアメニティセット(有料)を購入する必要があります。また、サウナの利用は入浴料とは別料金(2024年時点の情報では+300円程度)となっています。
このように、千年温泉は「大正ロマン」という情緒あふれるデザインコンセプトと、「黒湯の天然温泉」という強力なコンテンツを両立させた施設です。古くからの銭湯文化を大切にしながらも、現代の利用者が求める快適さや非日常感を巧みに取り入れた、神奈川を代表するデザイナーズ銭湯の一つと言えます。
しずの湯(座間市)
2025年2月には、座間市に「しずの湯」がオープンし、大きな話題となりました。この施設は、創業から57年の歴史を持ちながらも設備の老朽化などで惜しまれつつ閉店した「亀の湯」を、「株式会社yue」が全面的にリノベーションして蘇らせたものです。
この銭湯のコンセプトは、岩手県の景勝地「浄土ヶ浜」です。浴室はスペインから輸入したタイルを使用し、白く輝く流紋岩の岩肌(白いタイル)と、透明度の高い青い海(青色のモザイクタイル)を見事に表現しています。また、カウンターに岐阜県産スギの一枚板、サウナの外装に国産のスギ皮を使用するなど、内装に国産材を多用し、木の温もりを感じられる空間づくりも特徴です。
ただし、利用にはいくつかの注意点があります。「しずの湯」は現在、男性専用施設として運営されています(※将来的にレディースデーを実施予定)。また、入浴料金はタオルレンタル料込みで1,480円(2025年2月時点)となっており、いわゆる町の銭湯(公衆浴場)とは異なる、サウナ利用を前提としたプレミアムな価格設定です。訪問前には公式サイトで最新の営業形態をご確認ください。
御成桑拿(鎌倉市)
2025年に鎌倉に誕生した「御成桑拿(おなりさうな)」も、この文脈で注目すべき施設です。こちらはサポーズデザインオフィスが設計を手掛けた施設で、その洗練された建築デザインは圧巻です。
厳密には、公衆浴場としての銭湯ではなく、料金体系も異なる高級サウナ施設に分類されます。しかし、こうした高品質なデザインと温浴体験を融合させた施設が誕生していること自体が、デザイナーズ銭湯のトレンドと地続きの現象と言えるでしょう。
このように神奈川県内でも、伝統の継承から最新のデザインまで、多様なリノベーション銭湯が登場しています。神奈川県公衆浴場業生活衛生同業組合のウェブサイト「神奈川銭湯」などでも、こうしたリニューアル情報や各銭湯の特色が発信されていますので、チェックしてみるのも面白いかもしれません。
こだわりが光るサウナ設備

近年の爆発的なサウナブームは、デザイナーズ銭湯の設備充実に非常に大きく影響しています。多くの施設が、リノベーションを機にサウナ設備を新設、または大幅に強化しており、銭湯の集客における重要な要素となっています。
入浴料に加えて別途サウナ料金(300円〜500円程度が相場)が必要な場合がほとんどですが、一般的なサウナ専門施設に比べて安価に、本格的なサウナ体験ができる点が人気を集めています。
例えば、渋谷の「改良湯」では、定期的にアロマ水がサウナストーンに注がれるオートロウリュが導入されたサウナ室と、渋谷の空を感じられる外気浴スペースが完備されています。中野の「松本湯」は、オートロウリュ付きの高温サウナや漢方スチームサウナ、そして水深150cm(男湯)の深い水風呂など、サウナ愛好家(サウナー)も納得の充実した設備を誇ります。
さらに、大田区の「COCOFURO たかの湯」では、大音量のJ-POPと照明の演出が加わった「ミュージックロウリュ」や、水温8度に設定された(日によって変動あり)水風呂など、エンターテインメント性の高いユニークな設備が話題です。
もちろん、サウナだけでなく、高濃度炭酸泉やミクロの泡が特徴のシルク風呂、天然温泉(特に都内や神奈川では黒湯が多い)など、「お湯」そのものにこだわっている施設も多数あります。サウナ後の休憩(ととのい)スペースとして、静かな内気浴エリアや、リクライニングチェア(インフィニティチェア)を置いた外気浴テラスを整備する銭湯も増えており、各施設が創意工夫を凝らして快適な温浴体験を競い合っています。
空間を彩るアートな壁絵

銭湯の象徴といえば、浴室の壁に雄大に描かれた富士山のペンキ絵を思い浮かべる方も多いでしょう。一説には、1912年(大正元年)に東京・神田にあった「喜多の湯」が、利用者を喜ばせるために描いたのが始まりとも言われています。以来、湯船に浸かりながら広大な景色を眺めるスタイルは、銭湯文化の核の一つとして定着してきました。
デザイナーズ銭湯においても、この「壁絵」は単なる装飾に留まらず、伝統と革新が融合する、施設の個性を象徴する見どころの一つとなっています。
伝統モチーフの継承と再解釈
もちろん、リノベーション後も富士山や縁起物といった伝統的なモチーフを大切にしている施設は多くあります。ただ、そこには現代的なセンスによる「再解釈」が加えられ、空間演出の重要な要素として組み込まれている点が異なります。
例えば、豊島区の「五色湯」では、改修前から大切にされてきた縁起の良い「滝」のタイル絵が主役です。設計の妙は、このタイル絵の直下に水風呂を配置した点にあります。視覚的に流れ落ちる水(滝)と、身体で感じる水の冷たさ(水風呂)がダイレクトに結びつき、まるで滝壺に打たれているかのような没入感を味わえます。これは、絵と現実の体験を巧みに繋げた、非常に粋な空間演出と言えます。
また、町田市の「大蔵湯」では、日本画家・横山大観の作品をモチーフにしたとされる、鮮やかな「黄金富士」のタイル画が浴室の主役となっています。ペンキ絵とは異なる、タイル画ならではの輝きと重厚感が、圧巻の存在感を放っています。この神々しいほどに輝く富士に対し、浴室の他の部分はシックで落ち着いたトーンにまとめられており、その大胆な対比(ギャップ)が、空間全体に素晴らしい緊張感と高級感を生み出しているのです。
現代アートとの融合
その一方で、従来の銭湯のイメージを覆す、全く新しい現代的なアートを大胆に取り入れるケースも増えています。
象徴的なのは、渋谷の「改良湯」です。ここでは、ライブペイントユニット「Gravityfree」による巨大なクジラの絵が、男女の浴室をまたぐようにダイナミックに描かれています。施設のコンセプトである「渋谷 CULTURAL CROSSING」を体現するかのように、国籍や性別、文化を超えた多様な人々が集う大海を、雄大なクジラが回遊しているイメージを想起させます。
中目黒の「光明泉」では、若手の現代アート作家が手掛けた、デフォルメされたポップな富士山が描かれています。白を基調としたシンプルモダンな浴室空間において、このアートは伝統への敬意(富士山というモチーフ)と、現代的な感性(ポップな表現)が両立できることを示しており、銭湯に馴染みのなかった若者層へのフックとしても機能しています。
墨田区の「黄金湯」の壁絵も非常にユニークです。手掛けたのは漫画『きょうの猫村さん』の作者としても知られる、ほしよりこ氏。
一般的な一点透視図法の風景画とは異なり、物語性を感じさせる「絵巻風」のデザインになっています。
湯船でリラックスしながらぼーっと眺めていると、絵の中の人物たちのストーリーが自然と浮かんでくるようで、豊かな時間を提供してくれます。
アート体験の場としての銭湯
このように、デザイナーズ銭湯の壁絵は、浴室を彩る単なる装飾を超え、その施設の「顔」であり「思想」を表現するアート作品としての側面を強く持っています。
中島盛夫氏や故・丸山清人氏といった伝統的な銭湯絵師が守ってきた技術と、現代アーティストの斬新な感性がコラボレーションする場ともなっています。時には、練馬区の「久松湯」のように、壁面にプロジェクションマッピングを投影し、映像アートとして空間を演出する施設まで登場しました。
湯船に浸かりながら、リラックスした無防備な状態で本格的なアートを鑑賞できる。
これは、美術館やギャラリーでは決して得られない、銭湯ならではの稀有な体験価値です。
浴室全体がギャラリー空間へと昇華したデザイナーズ銭湯は、訪れる人々に心身両面からの癒しを提供しています。
デザイナーズ銭湯で心身リフレッシュ
この記事では、デザイナーズ銭湯がなぜ増えているのか、その背景にある業界の課題から、リノベーションによって生まれる新たな魅力について、具体的な施設例を交えながら解説してきました。
日頃の疲れを癒す場所として、あるいは新しいカルチャーに触れる場所として、デザイナーズ銭湯は今後ますます注目を集めることでしょう。最後に、本記事の要点をまとめます。
- デザイナーズ銭湯は伝統的な銭湯のリノベーション施設
- 設備の老朽化や経営者の代替わりがリニューアルの背景
- 燃料費高騰なども銭湯業界の経営課題の一つ
- 「古い」「暗い」といった従来のイメージを払拭
- 清潔感とおしゃれな空間で新たな客層を獲得
- 著名な建築家や設計事務所がデザインを手掛ける
- 今井健太郎建築設計事務所が多くの施設設計を担当
- 昔ながらの良さと現代的なデザインが融合している
- 東京には渋谷、中目黒、練馬、墨田などに点在
- 神奈川県内でも川崎や横浜でリノベーション銭湯が増加
- こだわりのサウナ設備を併設する施設が多い
- サウナ利用は別途料金が必要な場合があるので注意
- 壁絵は伝統的なペンキ絵から現代アートまで多彩
- 比較的安価な入浴料で非日常的な空間を体験できる
- 美術館を訪れるような感覚で日頃の疲れをリフレッシュできる